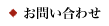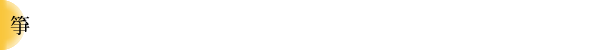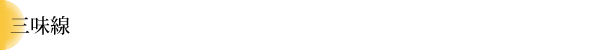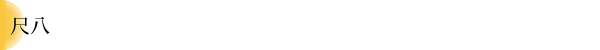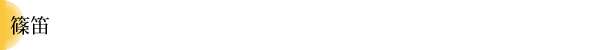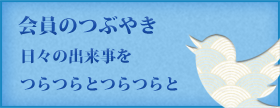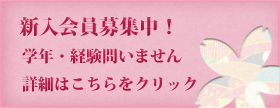箏は、前後にアーチのかかった横に細長い板状で内部が中空の胴に、13本の絃(糸)を渡して柱(じ)を用いて張り音程を調節し、奏者の右手に嵌めた爪(義甲)によって絃をはじいて音を出し演奏する楽器です。奏者の側の端を龍頭、逆を龍尾と呼ぶなど各部の名前が龍になぞらえられています。古くは雅楽に用いられ奈良・平安時代より独奏楽器として貴族に広く親しまれていましたが、江戸時代においては盲目の男性音楽家以外はプロの演奏家になることが許されませんでした。私たちはこの箏と、宮城道雄により開発された17本の弦を持つ十七絃という箏を演奏しています。
箏は、前後にアーチのかかった横に細長い板状で内部が中空の胴に、13本の絃(糸)を渡して柱(じ)を用いて張り音程を調節し、奏者の右手に嵌めた爪(義甲)によって絃をはじいて音を出し演奏する楽器です。奏者の側の端を龍頭、逆を龍尾と呼ぶなど各部の名前が龍になぞらえられています。古くは雅楽に用いられ奈良・平安時代より独奏楽器として貴族に広く親しまれていましたが、江戸時代においては盲目の男性音楽家以外はプロの演奏家になることが許されませんでした。私たちはこの箏と、宮城道雄により開発された17本の弦を持つ十七絃という箏を演奏しています。
 三味線は、四角状の扁平な木製の胴の両面に皮を張り、胴を貫通して伸びる棹に張られた弦を、通常、銀杏形の撥(ばち)で弾き演奏する楽器です。中国の三弦という楽器を盲人音楽家たちが改良したものが、歌や語りの伴奏や各地民謡などさまざまなジャンルに用いられるようになりさらに改良されてきました。本体は「天神」(糸倉)、「棹」(ネック)、「胴」(ボディ)から成ります。津軽三味線、地唄三味線、長唄三味線などジャンルによって種類があり、棹の太さなどの規格が異なります。私たちが主に用いるのは地唄三味線という中棹の三味線です。
三味線は、四角状の扁平な木製の胴の両面に皮を張り、胴を貫通して伸びる棹に張られた弦を、通常、銀杏形の撥(ばち)で弾き演奏する楽器です。中国の三弦という楽器を盲人音楽家たちが改良したものが、歌や語りの伴奏や各地民謡などさまざまなジャンルに用いられるようになりさらに改良されてきました。本体は「天神」(糸倉)、「棹」(ネック)、「胴」(ボディ)から成ります。津軽三味線、地唄三味線、長唄三味線などジャンルによって種類があり、棹の太さなどの規格が異なります。私たちが主に用いるのは地唄三味線という中棹の三味線です。
 尺八とは、竹製の縦笛です。息を吹き付けるところを歌口といい、手孔と呼ばれる孔が一般的に前面に4つ、背面に1つあります。様々な長さのものがあり、一寸長くなると半音低い音が出ます。最もよく使われるのが一尺八寸のもので、そのことから尺八と呼ばれるようになったという説があります。江戸時代には普化宗の虚無僧のみ吹くことが許されていましたが、明治時代に普化宗が廃止されたため楽器として普及しました。主な流派として琴古流と都山流があります。
尺八とは、竹製の縦笛です。息を吹き付けるところを歌口といい、手孔と呼ばれる孔が一般的に前面に4つ、背面に1つあります。様々な長さのものがあり、一寸長くなると半音低い音が出ます。最もよく使われるのが一尺八寸のもので、そのことから尺八と呼ばれるようになったという説があります。江戸時代には普化宗の虚無僧のみ吹くことが許されていましたが、明治時代に普化宗が廃止されたため楽器として普及しました。主な流派として琴古流と都山流があります。
 篠笛とは、竹製の横笛です。息を吹き付けるところを歌口といい、指孔(手孔)と呼ばれる孔が一般的に7つあります。篠笛は大きく「囃子用(古典調)」と「唄用」の二種類に分けられます。「囃子用」は祭囃子、神楽、獅子舞等、各地の祭礼に古来用いられてきた正確な音階のない篠笛です。「唄用」は三味線や箏など正確な音階があるものに合わせるため音階のある篠笛です。私たちは唄用の篠笛を用いて演奏しています。また、尺八と同じく様々な長さのものがあり、「○本調子」という書き方で表します。○には数が入り、数字が大きくなると長さは長くなり音は半音下がります。
篠笛とは、竹製の横笛です。息を吹き付けるところを歌口といい、指孔(手孔)と呼ばれる孔が一般的に7つあります。篠笛は大きく「囃子用(古典調)」と「唄用」の二種類に分けられます。「囃子用」は祭囃子、神楽、獅子舞等、各地の祭礼に古来用いられてきた正確な音階のない篠笛です。「唄用」は三味線や箏など正確な音階があるものに合わせるため音階のある篠笛です。私たちは唄用の篠笛を用いて演奏しています。また、尺八と同じく様々な長さのものがあり、「○本調子」という書き方で表します。○には数が入り、数字が大きくなると長さは長くなり音は半音下がります。